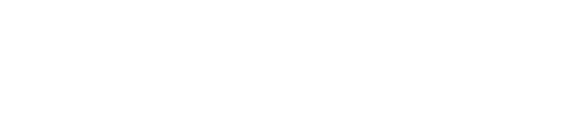フラホワBlog

コーヒーをこれからはじめる方へ
KiaOra!! すっかり秋めいて夜は寒いくらいですね。ホットコーヒーが沁みる季節です……え?コーヒー始める? ようこそ!そんなあなたのお手伝いができる事を祈って。 まずは、むずかしい事は置いておいて…。コーヒーって苦いもの。そう思っていませんか?もちろん、いわゆるブラックコーヒーは苦いものがほとんどかもしれません。でもその中に「甘味」や「コク(≠苦み)」「アロマ」 苦み以外にも感じられるコーヒーがあります。さらに、ミルクと合わせた「ラテ」系のドリンクや、浅煎りの「苦くない」ブラックコーヒーもあります…!! まずは気になるお店にGO!自分の好みを探してみましょう! ステップ1『好みの味を探す』 「おや…?おいしいかも…?」そう思えるコーヒーに出会うために、お店で飲んでみましょう。 全国にある大手チェーンであれば、いつでもどこでも「安定したクオリティ」で利用することができ、利用しやすいかもしれません。 個人で営業されている小規模のカフェ・喫茶店であれば、オーナーさんの好みや表現したい味が出せるのでコーヒーの「個性」が存分に発揮されているかも。 フラホワのように複数店舗展開しているカフェ・ロースターはその中間的存在。「いいとこどり」をしていると私は思います。 まずは一杯、オーダーしてみましょう!! ミルクたっぷり『ラテ』スッキリした口当たり『ドリップコーヒー(ペーパードリップ)』ちょっと通かも『アメリカーノ』 なんでもいいのですが、砂糖などで甘さが足されてしまうとコーヒー本来の味ではなくなるので、好きな味のコーヒーを探すとなると逸れるかもしれませんね。 勿論気分で変わることもありますから、飲み比べできると最高です! ステップ2『どんな豆だった?』 さて、「この味が好きかも…」に出会えましたか? ここでもう一歩踏み込んでみましょう。それは使われているコーヒー豆がどんな豆なのか? 『浅煎り』『中煎り』『深煎り』…『エチオピア』『ブラジル』『コロンビア』…『アラビカ種』『ロブスタ種』『ハイブリッドティモール』… みなさんが遠ざかる足音が聞こえます… ちょっと待って!難しく考えないで! まずは『焙煎度』を店員さんに聞いてみましょう! ものすごくざっくりですが『浅煎り』『中煎り(中深煎り)』『深煎り』の3つのどれだったのか? そこが分かるだけでも、傾向はつかめます!! ぜひ試して欲しい Wiremu的おすすめは浅煎り。フルーティなコーヒー本来の味が楽しめる&豆によって非常に個性に差があるので飲み比べるのが楽しい!! ちなみに焙煎については前回 Charlieが紹介していましたので、こちらもぜひ。コーヒー豆の焙煎って何? ...

コーヒー豆の焙煎って何?
キッチンで焙煎デビュー グッデイ!Charlieです🖐️僕が初めて焙煎したのは、今から10年とちょっと前のことでした。フラホワ泉店のキッチンで、Mickey社長がおもむろに取り出したのは、茶色くないコーヒー豆。 そして、銀杏を煎る用の金網。「これで焙煎してみようか」言われるがまま、コンロの上で金網をシャカシャカ。目を輝かせながらつぶつぶを見つめる僕。カップラーメンよりも早く出来上がったそれは——残念ながら、生焼けでした。 コーヒーの美味しさはどこからやってくる? ここで、コーヒー豆について簡単に説明を。コーヒー豆は、もともとはコーヒーノキという木に実っている、果実の種の部分を指します。 コーヒー生産者さんが収穫した実は、精製処理を施され、「生豆(なままめ)」と呼ばれる状態で私たちロースターのもとへやってきます。 コーヒーには800種類以上の香り成分が含まれていると言われていますが、この生豆から感じるのは、藁や草のような香りで、コーヒーの香りは全然しません。そう、皆さんが普段目にする茶色い豆とは、見た目だけでなく中身の成分もまるで別物。あの苦味や酸味、香ばしい香りのもとになる成分は、まだ生豆の中で眠ったままなのです。 そんな、THE素材なコーヒー生豆ですが、熱を加えることで驚くほどのたくさんの変化を遂げます。その変化をうまく引き出すのが何を隠そう、「焙煎(ばいせん)」です。 焙煎によって、豆の中に含まれる成分が化学変化を起こし、香りや酸味、苦味のもととなる成分が次々と生まれ、ようやく私たちが知る“コーヒーらしい味わい”が姿を現すのです。 焙煎とコーヒーの味 ご存知の通り、コーヒー豆にはさまざまな産地や品種、精製方法があり、自分好みのコーヒーを見つけるためのキーワードになっています。でも実は、コーヒーの美味しさの大部分は「焙煎」によって決まると言っても過言ではありません。産地や品種が同じ生豆だとしても、焙煎の加減でまったく違った味わいを作り出すことができます。もちろん、産地や品種、精製方法によっても風味は変わりますが、焙煎の加減による味の変化は、それらを上回るほど大きいんです。 たとえば、パンの小麦の種類よりも、自分好みのトースト加減の方が、「これだ!」っていうのがありませんか?コーヒーもそれと同じ感じで、焙煎度合い(=焼き加減)を意識するだけで、「あ、これ好きかも」が見つかる確率がぐんと上がりますよ! 酸味と苦味のカンケイ コーヒー選びに役立つ「焙煎度合い」簡単に説明するとこんな感じです。 焙煎前:生豆(食べられない) 浅煎り:酸味と香り(軽やかで明るい印象) 中煎り:(浅煎りより酸味がマイルド) 中深煎り:(深煎りより苦味がマイルド) 深煎り:苦味とコク(重厚で落ち着いた味わい) 焼き過ぎ:焦げた味 焙煎が進むにつれて酸味は弱まり、苦味が強くなります。 この焙煎度合い、お店によっては「○○ロースト」と表記されることもありますが、実はお店の志向や地域などで基準がまちまちで、主観で決められることも少なくありません。 なので、あまり難しく考えず、・浅煎りのものほど「酸味」の要素が強い・深煎りのものほど「苦味」の要素が強いと捉えるくらいでちょうど良いのかもしれません。 ここでひとつアドバイス!もし、自分が好きな味が何か分からない時は、浅煎り、中煎り、中深煎り、深煎り、、とひと通り飲み比べてみて、自分好みの焙煎度合いを見つけるところからスタートしてみましょう。店先で試飲のコーヒーをもらったら、「これはなに煎りですか?」なんて聞いてみるのもいいかもしれませんね! ちなみにフラホワでは、コーヒー豆の味わいをFRUITY(浅め)・MILD(中間)・BITTER(深め)で分けています。 エチオピア バンティネンカ農園ナチュラルは、同じ豆でも、3種類全ての味わいをご用意しているので、ぜひ飲み比べてみてください☕️...

ゲイシャコーヒーとは?
なになに?ゲイシャコーヒー?芸者コーヒー? こんにちは、フラホワのHannhaです!初めてこの品種を聞くとそのように連想されがちなコーヒーでもあり、コーヒー好きの間では特別な一杯としてお店のメニューにあると思わずテンションが上がってしまう魅力たっぷりな品種!! 今回はコーヒーの女王とも呼ばれる『ゲイシャコーヒーとは?』をテーマにスタートしようと思います。 ゲイシャのルーツはエチオピア ゲイシャコーヒーの『ゲイシャ』は、このブログの冒頭にある日本の「芸者」とは実は全く無関係。原産地であるエチオピアの「ゲシャ」という地域に由来する名前で、この地で発見されたアラビカ種(コーヒーノキ属の一種)の突然変異によって生まれた品種です。 ゲイシャコーヒーはなんで有名なの? 2004年、パナマのエスメラルダ農園が国際品評会「Best of Panama」に出品したゲイシャコーヒーが、当時の最高価格で落札されました。この出来事は「ゲイシャ・ショック」と呼ばれ、世界中のバイヤーやロースターがゲイシャ種に注目するきっかけとなり有名な品種としてその名が世界各国に広まりました。 ゲイシャコーヒーはなぜ高価なの? コーヒー屋さんでは1杯1,000円以上もするリッチなコーヒー。高価な理由の一つとしてゲイシャコーヒーは栽培が難しく収穫量も限られています。さらに、標高1,500m以上の高い土地で涼しい気候でしか育ちません。土壌や気候の条件が厳しく高度な農業技術が必要な品種で、丁寧に育てられ、手間を惜しまない精製方法が求められます。世界全体のコーヒー生産量に占める割合もごくわずかなため希少価値が非常に高いのです。 香りと味の圧倒的な個性 ゲイシャコーヒーの最大の特徴は、その香りと味わいです!ジャスミンやバラのようなフローラルな香りでベルガモットやシトラスのような爽やかな酸味。はちみつや白ぶどうのような甘みを持っています。苦みがほとんどなく、まるで紅茶のような繊細さで口に含むとコーヒーが持つアロマが広がります~! ゲイシャコーヒーの栽培地と味わいの特徴 ※パナマ レリダ農園 ゲイシャコーヒーは元々エチオピアのゲシャ村で発見された品種ですが、現在では中南米やアジアなど世界各地の限られた地域で栽培されており、育つ土地(テロワール)によって驚くほど風味が変わります。世界中のコーヒー愛好家が『格別』と認めるほど香り・味・質感の全てにおいて際立った個性を持っています。 ※ゲシャビレッジ それぞれの国のゲイシャが持つ個性を、①香りの特徴②酸味の傾向③甘み・余韻④質感・口当たりの順にご紹介します。 パナマ産ゲイシャ ①:ジャスミン、ローズ、ラベンダーなど華やかさ②:ベルガモット、オレンジのような明るさ③:はちみつ、白ブドウのような自然な甘み④:シルクのように滑らかで繊細 エチオピア産ゲイシャ ①:野性味のあるフローラル感やスパイス感②:レモン、ライム、ベリー系の爽やかさ③:果実感と複雑な余韻④:軽やかで紅茶のような質感 コロンビア産ゲイシャ ①:ジャスミン、ラベンダーなど上品で控えめ②:白桃、アプリコットのような丸みのある酸味③:キャラメル、はちみつのような甘み④:滑らかでバランスが良い...

コーヒー豆を美味しく長持ちさせる保管方法
こんにちは!Lilyです! みなさまは購入したコーヒー豆をどのように保管していますか?実は、コーヒーを美味しく楽しむためには、豆の保管方法もとても大切。環境を整えて豆たちを保存してあげることで、より長く、美味しい状態でコーヒーを楽しめます! 今回は「コーヒー豆を美味しく長持ちさせる保管方法」について、基本からちょっとした応用まで、解説していきます。ぜひ最後までお付き合いください! ✦ コーヒー豆の『鮮度』を保つこと コーヒー豆は、実はとても繊細で、「生鮮食品」に近い扱いが必要です!そのため、鮮度を保つことが、長く美味しく楽しむためにとても重要。 コーヒー豆は焙煎直後から、少しずつ美味しさが空気中に逃げ出していきます。さらに豆の表面や内部では「酸化」が進み、油分が劣化することで風味が損なわれて行ってしまうんですね… まず知っておきたいのは、コーヒー豆の鮮度を保つうえで注意が必要な「4つの敵」! それは 、酸素・光・高温・湿気。 ●酸素:豆は空気に触れると酸化し、風味も香りも少しずつ落ちていきます。●光:紫外線などの光でも劣化が進んでしまいます。●高温:温度が上がると酸化が加速。特に夏場のキッチンは要注意!●湿気:水分は豆の劣化を早めるだけでなく、カビの原因になることも… この4つをできるだけ避けることが、コーヒー豆を美味しく保つための第一歩。まずは、「密閉できる容器に入れ、直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に置く」だけでもいつもより、長く美味しくコーヒーが楽しめます。 過去のSallyの記事でも詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください!『プロがおすすめ!コーヒー豆の保管方法』 ✦ コーヒー豆の保管場所 コーヒーラバーのみなさまも、コーヒー豆を保管する時に、常温・冷蔵・冷凍の結局どれが正解なの?と一度は悩んだことがあるはず… 注目ポイントは、コーヒー豆を購入してどのくらいの期間保管するのか。期間によって保存環境を変えるのがおすすめです! ●常温保存 もっとも一般的。直射日光を避け、涼しくて乾燥した場所で保管すれば、日常的に飲む分には十分です。1~2週間で飲み切る場合は常温でOK ●冷蔵保存 温度が低いため酸化は遅くなりますが、冷蔵庫内の匂いが移りやすい点には注意です…そのため、密閉容器が必須。飲む頻度が多く、頻繁に出し入れするなら常温保存のほうが扱いやすいかもしれません。温度差で結露が出るため、あまり推奨はできませんが、夏場など、高温多湿の環境で2週間を超える保存におすすめです。 ●冷凍保存 1ヵ月を超える長期保存の場合はこちら。ただし、急激な温度差で結露がつくと豆が劣化するので、飲む前に冷蔵庫でゆっくり解凍するのが安心。粉は劣化が早いため、豆のまま冷凍する方が長持ちします。こちらも温度差で結露が出るため、あまり推奨はできませんが、長期間保存が必要な場合は冷凍しましょう。 期間はあくまで目安ですが、その時の環境に合わせて、ぜひ保存方法を変えてみてください! 一番は、なるべく温度変化がない状態で、早めに飲み切ることですので、できれば、買う量は「1ヵ月以内に飲み切れる分」を目安にすると、常に美味しい状態でコーヒーが楽しめます! ✦ コーヒー豆の保管容器 次に豆の保管容器についてです!こちらもコーヒーを淹れている方は、一度は悩みますよね…! もちろん、購入した際に入っている袋や箱でも、未開封であり、袋にガス抜きバルブがついていれば、そのまま保管しても問題はありません。ですが、開封後はなるべく空気に触れないよう、密閉容器に入れるのがおすすめ。...
コーヒー豆を美味しく長持ちさせる保管方法
こんにちは!Lilyです! みなさまは購入したコーヒー豆をどのように保管していますか?実は、コーヒーを美味しく楽しむためには、豆の保管方法もとても大切。環...

ブルーマウンテンはどうして高価なの?
こんにちは、ドミンゴと申します。 今回のお題、ブルーマウンテンはどうして高価なのか? ブルーマウンテンはコーヒーが詳しくない方でも聞いたことがあるのではないでしょうか? そのまま和訳すると青い山? 由来はブルーマウンテン山脈の山々が青みがかった霧に包まれて青く見えることからその名がついたと言われています。 そしてコーヒーが育つブルーマウンテン地域は標高が高く、朝晩の温度差が大きいのが特徴です。 この地域の土壌は火山性であり、ミネラルが豊富なためコーヒー豆に独特な深い味わいとバランスの良い酸味を与えてくれています。 ブルーマウンテンコーヒーの歴史 18世紀初頭、ジャマイカがイギリスの植民地だった時代にアフリカから持ち込まれたコーヒーの苗木が始まりです。当初は低地栽培されていましたが、ブルーマウンテンの高地へと移されたことで品質が飛躍的に向上。 この地域特有の気候と土壌の条件が、ブルーマウンテンコーヒーをより進化させ、現在のような高い評価を得られるようになりました。 場所は中米カリブ海に浮かぶ島国、ジャマイカになります。ジャマイカで連想する物と言えば何でしょう? レゲエミュージック、ダンス、ウサイン・ボルト(100m世界記録保持者)、陽気、自然が多い・温暖などではないでしょうか? しかしコーヒーも有名でランクも高く、とても高価な物が多いです。なぜでしょうか? 「他の国と一緒で高いものもあるけど…ピンキリでしょ?」 確かに作物なのでそう言った事もありますが… その中でもブルーマウンテンはほとんどが高価で希少性が高く、『コーヒーの王様』とも言われます。 ※ぜひ合わせてお読みください ↓↓↓ アリのブログ記事『ハワイ・コナってどんなコーヒー?』 ジャマイカ政府が定める基準に基づき、主に豆のサイズや欠点豆の数によって等級が分けられます。 ●ブルーマウンテン No.1 ・最高級グレード ・豆の大きさが最も大きく、欠点豆がほとんどない ・風味のバランスが非常に良く、豊かな香りと上品な酸味が特徴 ・市場で最も高値で取引される ●ブルーマウンテン No.2 ・豆のサイズはやや小さめだが、風味はNo.1に近い ・若干欠点豆が含まれる可能性ある ・価格はNo.1よりやや安い ●ブルーマウンテン No.3 ・より小さめの豆で、欠点豆の許容数が多い ・一般的には家庭用やカジュアルなカフェ向け ・香り・味のバランスは落ちるが、ブルーマウンテンらしい風味は楽しめる また、標高約800m〜1200mで指定された山岳地帯での収穫のみ「ブルーマウンテン」として認定されます。 ブルーマウンテンの生産エリアは、狭いエリアに集中している為、自然災害や病害虫の被害などが発生した際のダメージは大きく、過去もハリケーンの被害(ハリケーン・ギルバート1988)などで壊滅的なダメージを受け、生産量が激減し、高騰を繰り返してきました。コーヒー栽培エリアは海岸部とそれほど離れているわけではない土地柄、コーヒー生産を行う1000m以上の山々までの道のりは急斜面となっており、土砂崩れなど天候に大きく左右されやすい過酷な土地でもあります。農機が入るのも困難なので収穫から豆の乾燥までほぼ全ての工程が手作業となります。 政府による厳格な認証、法整備、限られた生産エリアというだけでなく、気候条件上不安定な土地柄という事も、ブルーマウンテンに特別な風味と希少性を高めてきた要因です。...

コマンダンテを2年使ってわかった、手挽きミルの魅力と実力
こんにちは、フラホワのニカウです! 僕はバリスタではなく、コーヒーを飲むことが大好きな、オンラインショップ担当の裏方メンバーです。 そんな僕がコマンダンテを2年愛用してわかったことを、今回のテーマにしてみようと思います。専門的な知識というより、考え方や気持ち、生活の変化などの面を綴ろうと思います。お付き合いくださいませ! 電動から手動へ カリタのナイスカットミルという電動型からコマンダンテに換えたのは、2023年の春頃のこと。それまで「コーヒーを挽くなら電動が楽でいいに決まってる」と思っていたのですが、今では手挽きの時間を毎日楽しみにしています。豆を挽くことからコーヒーブレイクが始まります。 手挽きミルの「面倒くささ」がご褒美に変わる ご存知の通り、コマンダンテは安くありません。手挽きミルとしてはおそらく価格も最高峰。そして、電動ミルのようにスイッチ一つで待つだけではなく、手間もかかります。 でもそのひと手間こそが、僕にとっては「楽しい儀式」になりました。 朝、豆を量って入れて、ゆっくりと挽く。コリコリという、低くて心地よい音と手に伝わる確かな感触。これはナイスカットミルでは得られなかった感触。きっとまだ寝ている子供たちも、機械の音よりも心地良い朝の知らせになっているはず。 コマンダンテを使い始めてから、コーヒーは飲み物じゃなくて時間になりました。それがコマンダンテを使い始めてすぐに感じたこと。 デザインの良さが所有欲を刺激 まず目に入るのが、潔い美しさ。金属のブラックボディと、ウッドのハンドル。クリアなビーンジャーとのコントラスト。キッチンに置いてあるだけで絵になります。ウッドボディもありますが、下地はどれも丈夫な金属製。 子供達も「何それ?カッケー!」と興味津々。さすがドイツのデザイン。余計な装飾を排除した、シンプルで機能的な美しさ。バウハウスのデザイン思想を感じるのは僕だけなのでしょうか。 そしてブランド名『コマンダンテ』なんて力強い響き!とっておきの頼もしいツールって感じがしませんか?笑そんなお気に入りの道具を毎日使えるって、こんなに心地良いものなんだと気づかされました。 性能は見た目以上にプロフェッショナル コマンダンテの刃はニトロブレードという特殊鋼製。この刃がとにかくすごい。 挽き目の均一性が圧倒的で、ペーパードリップ用でもエアロプレス用でも、粒度のブレが超少ない。擦り潰すのではなく、カットしているために微粉もかなり少ないことに驚きます。微粉が少ないと雑味も出にくく、クリアな仕上がりになります。世界各国のバリスタチャンピオンが愛用する理由がよくわかります。 挽き目の調整ダイヤルで細かく設定できるから、豆や抽出方法に合わせて微調整も自由自在。これはナイスカットミルと比べても明らかに上。ナイスカットミルの一番細かい設定よりもはるかに細かくカットすることも可能。 ちなみに、コマンダンテの調整ダイヤルは、コンコンコンと音を立てながら回ります。この、コンコンコンという音は「クリック」と呼ばれていて、12クリックで1回転する仕組み。三又のツマミの1本を目印にすれば、見ただけで今何クリック目かわかるようになりますよ!また、ハンドルが回らなくなる0クリックになると、「カチ」と音が変わります。この状態でハンドルを無理に回してしまうと… 刃がダメになって顔面蒼白。絶対に0クリックの状態で回さないようしましょう! 僕は浅煎りのコーヒーをよく飲みますが、コマンダンテにしてから抽出の安定感がぐんと上がった気がするんです。基本、30クリックで挽いています。ダイヤル2回転半ですね。「なんで今日だけ味が違う?」という謎のブレが減ったのも、コマンダンテのおかげ。間違いない。 しかも、浅煎りの豆って結構硬いんですが、コマンダンテならとてもスムーズ。引っかかることなく滑らかに回せます。すごい切れ味! 耐久性はとても高い! コマンダンテを使うのは、多い日で1日3回。平均すると年間500回ほどかと。2年使っても何のストレスもありません。刃の切れ味も衰えていないし、回転もスムーズなまま。メンテナンスは半年に1回程度です。 そのメンテナンスはとても簡単。調整ダイヤルをどんどん緩めてダイヤルを取り外せば、簡単に分解できて掃除も楽。精密だけどシンプルで、このタフさ。なんかかっこいいですよね。 メンテナンスと言っても、難しいことをしているわけではなく、中に残っている古いコーヒー豆の破片を刷毛でささっと取り除くだけ。ブレードは危ないし、錆びたら困るので手袋は必須です。 ...
コマンダンテを2年使ってわかった、手挽きミルの魅力と実力
こんにちは、フラホワのニカウです! 僕はバリスタではなく、コーヒーを飲むことが大好きな、オンラインショップ担当の裏方メンバーです。 そんな僕がコマンダンテ...