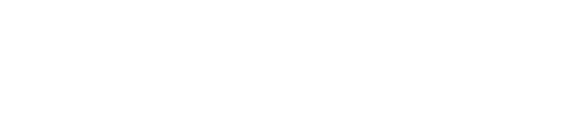ラオスコーヒープロジェクト Laos Coffee Project Part.4 最終章
今回の訪問の目的はFWCFオリジナル精製!独自のFermentation(発酵&精製)の実現!
滞在期間内の限られた時間の中でソンプーさんの農園、ウェット&ドライミルのキャパに適合した精製でなければ実現出来ない...チェリーの味わいも含めて収穫時期後半だった事もあり本当に充実した時間だったと思います。



天候に恵まれ、エンさんとソンプーさん、ご家族親戚の皆さんの献身的な協力により一つの精製方法『ブラックハニー』に行き着きました。
是非、ダンサワーンの特徴を出したい!
その為には通常のブラックハニーよりも多めのチェリーの皮(カスカラ)とミューシュレージの付着と36〜48時間小山盛に重ねた状態で発酵乾燥を実施し、次の過程で徐々に山盛りをほぐして行き、最終的は24日間掛けてフラットな状態で乾燥を重ね、通常の1.5倍の熟成かつ乾燥工程を経て仕上げられました。





産地の気候は変わり易く、雨季と乾季があると言われるコーヒー産地ですが、地域によっては様々で亜熱帯気候地域では乾季でも雨は降りますし、雨が降って乾燥して来たパーチメント(殻付きのコーヒー豆)が濡れたりするとカビの発生を招いたり、コーヒーの味わいに多大な影響を及ぼす原因になるので本当に神経を使うプロセスなのです。
気を抜けない!相手はコントロールの効かない『天候』だからです...


結果、丁寧に仕上げてもらった今回のロットは『甘さ』に関してはかなり格別!
長めに熟成させることによる期待していたフルーツ感は、ブラックハニーならではのブルーベリーやプラム感溢れる『芳醇な』味わいのコーヒーが出来上がりました!!

FWCFらしいネーミングとして、NZゆかりのダブルショットのエスプレッソ=LONG BLACKと通常のブラックハニーよりも長めの熟成を重ねてLONG BLACK HONEYと名付けて販売開始しました〜
そもそもティピカという品種に興味を持ち、その歴史はエチオピアの原種がイエメンでティピカになり、その後インドネシアへ...最初に述べた様にラオスにそのティピカ種がフランス人によって持ち込まれて始まったコーヒー栽培は100年以上(Since1905 )今も続いている...


現地の人達:ソンプーさんはじめ皆んなが声を揃えてラオスの在来種はティピカ種!
今は耐病性に強く生産性が高いカティモール種(ティモール&カツーラ:ハイブリット種)が耐病性の弱いティピカを抜き主力種となっている。
そうは言っても彼らはティピカを絶やさないように頑張っています。

SUSTAINABLE
コーヒー業界として重要なKEY WARDです。
農園を視察後、ソンプーさんの奥さんが家庭料理を用意してくれて伝統的なスティッキーライスを手で頬張る!ライスも2種類準備してくれるという素晴らしいおもてなしをして頂けました〜何と!ソンプーさんの家に『焙煎機』が...
そして彼らからミッキー焙煎教えてよ〜のオファーが...僕のロースター魂はもちろん『Sure,Why Not?』...彼らは僕の焙煎に興味津々...
これがスペシャルティコーヒー焙煎だ!と言わんばかりに彼らにとっては目から鱗の『浅煎り』を披露〜かなりの年代物...どうやらJICA絡みで手に入れた様な話をしていました...
煙突もなく排気はそのまんま...プロパンガスを繋いでワイルドな屋外焙煎!


GIESENとは勝手が違いましたが基本は一緒、浅煎りを仕上げて彼らはその焙煎度合いにもビックリ!焼き立てよりも明日に飲んだ方が美味い!のですが、我々には時間がなかったので持参したエアロプレスとソンプーさんが大切に使っている(かなり年季が入っている)V60の2種類で抽出〜そのフルーティな味わいに驚愕!
これ、本当に俺のコーヒーなのか??って...奥さんも『美味い』って親指立ててくれました。
でも好みはいつものビターな深煎りの方だったと後でこっそり聞きました(笑)

そもそも浅煎りや中煎り、深煎りと言うよりも『こんな感じ』と言うサードウェーブ前の90年代のコーヒー感覚はまだラオスで根強いと思います。
情報が足りないし少ないし、まだこれからのポテンシャルが溢れている国だと思います。
当然、今まで語って来たコーヒーの精製についてもまだまだコンサバティブな状況です。
10年前、いや5年くらい前のタイやインドネシアのコーヒーはこのラオスと同じ状況だった事でしょう...

コーヒー業界は日進月歩です。
FWCFとしても常に『進化』を求めて走り続けています。
SUSTAINABLE & PROGRESSIVE
『持続性と発展』


世界にはもっと美味しいコーヒーがあります。
生産者なくして美味しいコーヒーは生まれて来ません!
ラオスのコーヒー発展の為に汗を流して行きます。