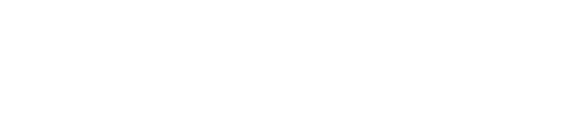コーヒーの精製について〜自称Mr.ファーメンテーション(発酵)のオタクな世界観Part.3 最終章〜
これぞ『進化型』!と呼ばれる嫌気性発酵Anaerobic ~ 進化型のファーメンテーション
⑤アナエロビック(嫌気性発酵)
正に『ファーメンテーション発酵マジック』
この発想はワインの原料となるブドウの精製から流用されていて、発酵プロセスの際に微生物が有機物(コーヒーチェリー)を分解して生成する物質が新たなコーヒーフレーバーを生み出しています。

Anaerobic嫌気性発酵に関してはバラエティ豊かな手法(密封式プラスチック製の樽~最新のステンレス製で気圧/ph/温度やモスト噴射機能など高性能な専用タンクなど)が世界に広がっていますが、そのパイオニアと呼ばれている方が以前FWCFでも取り扱った事のあるコスタリカのカフェ・デ・アルトゥラ精製所のエステバン氏の好奇心だったと言われています。窒素(ニトロ)を充填し、酸素を除去したタンクの環境を作り上げるアイデアです。

“Mossto”とは英語ではMustと呼ばれる自然な嫌気性発酵中に生成される液体で、粘液質とコーヒーチェリーなどで形成される状態のことです。
元々はワイン用語で、ブドウ圧搾後、果汁・果皮・果肉・種子などが混ざった状態のことを指します。
モストを再循環させるポンプを備え、発酵中のコーヒータンクの天井からモストの雨を降らせることで、コーヒー豆を常に微生物と接触/循環し、コーヒーの嫌気性発酵を維持させる目的で使用されています。
同様にカーボニック・マセレーションもAnaerobicの代表格*窒素は使用しない
「カーボニック」= 炭酸(二酸化炭素)
「マセレーション」= 漬ける
の意味で、二酸化炭素に漬けて発酵させると言った意味になります。
元々は、ワインの精製方法で一部の地域で行われているようで、有名な「ボジョレー・ヌーヴォー」がこの発酵方法で生産されているとの事です。
ワインの精製とコーヒーの精製は本当に結びつきが強いものなのです。
味わいの特徴は様々...一般的にスパイシーでまろやかなフルーツ感、ワイン感...
*但し、精製差や生産者差、出来栄えには賛否両論あります...
アナエロビックにはナチュラル、ハニー、ウォッシュドなど様々...
生産者の想いが込められています。
発酵の仕組みについて文字にすると超複雑(まるで化学の授業の様な専門用語の乱立...)
コーヒーの発酵の元になるのは、ミューシュレージとそれに付着している微生物。
ミューシュレージには糖分やペプチンが含まれていて微生物がこの成分を分解する事で発酵がおき、独特の風味を生成します!
a.微生物の活動(酵母やバクテリア)はミューシュレージのスクロース(糖分)やペクチンを分解
→グルコースやフルクトースなどの代謝副産物を生成
b.代謝副産物の分解
→アセトアルデヒドやエタノールなどの物質を生成
c.酸性物質の生成
→更に反応し、クエン酸や乳酸、酢酸などの酸性物質を生成
d.香りの生成
→微生物の活動によるエステル化合物はパイナップル、リンゴ、ブドウ、バナナなどの様々なフルーティな香りをもたらす
ジャコウネコの体内で発酵されたコピ・ルワックは今まで綴ってきたa~dの科学的アプローチでは出来ない発酵です。

『最高の人生の見つけ方』という映画で語られた一言で今も存在感のある究極の発酵コーヒーという地位を築いています。映画好きの僕にはたまらないフレーズでした...
e.最初のペクチンとスクロース以外に、果肉除去したコーヒーのタネ(豆)に含まれるアミノ酸がアルコールと反応しエステル化合物をさらに作り出します。
そもそもコーヒーは発酵食品!と語って来ましたが、以上が発酵の仕組みなのです。
ナチュラルはもちろん、ハニーやウォッシュドのコーヒーでさえもパルピング後夜間の涼しい時間を利用して発酵槽と呼ばれる槽の中で実施されます。


発酵過程を経ず、乾燥されたコーヒーは本当に味気のないコーヒーになる事が検証されていますので、通常のコーヒー精製に程度の差はありますが、必ず発酵過程を経て美味しいコーヒーが出来上がっているのです。
通常は以上の様な好気性発酵(こうきせいはっこう)で微生物は酸素を好むものなのです。
現在販売中のタイのDoi SaketはLactic Process はヨーグルトの持つ乳酸菌と通常のコーヒーの持つ発酵のダブル発酵の正に超好気性発酵と言える発酵です〜

以上述べてきました好気性発酵=通常の発酵とは対照的に『酸素』を含む外気に触れさせない発酵をおこなうのが、嫌気性発酵という事です。

コーヒーの嫌気性発酵では、果肉が付いたままのコーヒーチェリー、またはミューシレージ付きの状態で、発酵時のガスを逃がす逆止弁の付いた密閉容器に移され発酵がおこなわれます。


発酵時のガスで密閉容器の中の空気(酸素)が外に出され、容器内は酸素のない環境で活発に活動する微生物によって発酵が進むため、これまでの好気性発酵では成し得なかったフレーバーが生み出されます。


酸素を好まない微生物の代表が酵母、酸素がない状態の発酵では糖分が分解されて、さらに酸味がまろやかになる事が検証されていて、アントシアニンやタンニンの影響でCherryの果皮は紫ピンクに変色し、さまざまな化学反応によりイチゴやラズベリー、バナナ、バブルガムのようなフレーバーが生み出されるところが現在のトレンドたる所以です。

このように、コーヒーの生産処理で嫌気性発酵をおこなうことでアナエロビックは発酵感のある強いフレーバーを生み出すことが可能になりました。
過去に取り扱った様々なファーメンテーション
《ワイニーWiney》
以前扱っていたパナマのハートマン農園のワイニーは理想のワイニーティストでした...チェリーの水分値を高めに維持して内部発酵させて果実味を強くした手法
アフリカンベッドであまり広げない状態(フラットではなくレイヤー式)で層になる様に3日程度乾燥させて30分毎位に攪拌させたり、山積みに積み重ねてパテオ(コンクリート床)で1~2日程度とか色々なレシピがあります。
《ファンキーナチュラルFunky Natural》
以前扱っていたニカラグアのリモンシージョ農園の正にファンキーな手法。
収穫したチェリーを袋に入れた状態で水をジャブジャブ注ぎ、水に漬け込み発酵を強める為に日照時間が強い時間帯に直射日光に当てて発酵温度を上げていくやり方
《ペルラネグラPelra Negra/Black Peal》
BlackPerl黒真珠と呼ばれる手法で以前扱っていたニカラグアのエスコンディーダ農園のロットは特別感あり過ぎで好みの分かれる味わいでした。唯一無二の味わいで個人的には好きでした...ブラックハニーで仕上げたパーチメントを冷暗所(倉庫内)の黒ビニール(農業用のシート)に薄く敷き詰めて、更に上から黒ビニールで密封して仕上げて行きます。ブルーチーズの様な風味に仕上がり、甘味は独特で、かなりクセ強の個性的な味わい。

《ダブルファーメンテーションDouble Fermentation》
ナチュラル+ウォッシュド(又はハニー)の良いとこ取りの手法で以前はニカラグアのエンバシー農園やコロンビアのロス・モリノス生産組合パカマラ種の手法。
先程触れたワイニーのやり方の山積みでナチュラル(ワイニー)後、パルピングしてウォッシュドで仕上げる事により、味わいも発酵感とスッキリ感の一粒で2度美味しい味わい。

《スウィートシャワーSweet Shower》
コーヒー大国ブラジル(世界No.1の生産国)でも良いアイデアは生まれていました。
以前扱っていたイルマス・ペレイラ農園の手法。スウィートシャワーと名付けられた製法の特徴は、収穫したチェリーをカルモ・デ・ミナスの冷たい湧水(7-8℃)で満たされたタンクに14-15時間漬けておく事により、チェリーが低温に保たれ、酵素反応による発酵を防ぎ、発酵工程によって反応する糖の消失を防ぎ、チェリーの糖度を維持することが出来ます。
その後、パルプドナチュラルもしくはナチュラルとして、アフリカンベッドでの乾燥工程に移行していきます。 収穫したチェリーそのものの糖度を維持する為に、ドライファーメンテーションなどと異なる軽やかでフルーティな甘みの溢れるブラジルコーヒーを生み出しています。

《ダブルパスDouble Pass》
こちらもブラジルのイルマス・ペレイラ農園の手法。
通常ボイアと呼ばれるフローター(か完熟豆)は2次処理(格下)に回されますが、このボイアを水に18−20時間漬けてボイアの乾いたカスカラ(表皮)を柔らかくします。その後、パルピングしてウォッシュドで仕上げる事により明るい酸も感じられ、熟した甘味や旨みのあるコーヒーになります。
まだまだ沢山のアイデアが~日進月歩で新たな味わいが作り出されています。
Fermentation(発酵)の可能性...Still On The Road...