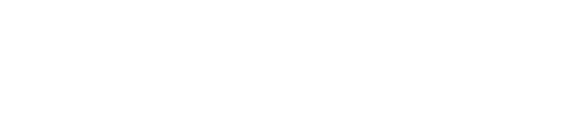コーヒーの精製について〜自称Mr.ファーメンテーション(発酵)のオタクな世界観Part.2〜
地域性やスペシャルティコーヒーの隆盛期2010年以降飛躍的に新しいトレンドとして過去10年で飛躍的に伸ばしている精製方法が③セミウオッシュド/パルプドナチュラル(正式名称)=ハニー(コスタリカ)です。


これはコスタリカや中米で興った『マイクロミル革命』〜通常、高地の生産地(標高1,500〜2,000m)で収穫したチェリーは電気や水道/灌漑設備の関係で低地の大型の精製所(町や村の精製所)まで運ばれて精製を行って来ました。その流れをいくつかの農園や生産者等で共同で小さな(マイクロ)精製所を作って採れたてのチェリーを新鮮なうちにパルピング(水洗皮剥き処理)や天日乾燥させる“ムーブメント”(一種の精製工程の革命)が起きました!


ここで登場したのが正式名称は『パルプド・ナチュラル』=『ハニー』(主にコスタリカでの呼称)なのです。
大義としてはウォッシュドに分類されパルピング(皮剥き)して水洗式で仕上げる精製ですが、①との大きな違いはパルピングの後の処理の仕方です。セミウォッシュドはパルピング後ミューシュレージの付いた状態で棚干し過程に入ります。

レシピと呼ばれる『精製プロセス(過程)』は生産者により様々です...

写真左がウォッシュド、右がハニー
発酵槽で〇〇時間~〇〇時間寝かすレシピ、パルピングの度合い(ミューシュレージと皮の残り具合)を調整出来るミューシュレージリムーバーを保有している生産者による多様なハニー(ホワイト/イエロー/レッド/ブラックetc)...マイクロミルの発展、世界のスペシャルティコーヒーの新たな味わいへの渇望...中米コスタリカで大きく発展した『ハニー』は今ではメジャーな呼称になりました。
取り立てのチェリーをその場で精製する〇〇ハニーは『個性的な味わい』を実現させる正にスペシャルティコーヒー業界の革命となったのです~
A:ホワイトハニー★ウォッシュドとほぼ同様と思われますが、ミューシュレージが極小

B:イエローハニー★ミューシュレージが30%程度残存/最も安定的でメジャーな仕上げ。甘さとスッキリさ、キレも感じます。

C:レッドハニー★ミューシュレージ&皮が50%程度残存/コクとフレーバーが特徴

D:ブラックハニー★ミューシュレージ&皮が70%程度残存/ワイニー感が特徴

フラホワの販売中のコーヒーは精製方法にとにかくこだわりを持ち、色々な精製のコーヒー豆の販売を手掛けています。*ウォッシュド/ナチュラル/レッドハニー/スマトラ式

セミ・ウォッシュドと呼ばれるコーヒー精製に中に④スマトラ式も含まれます。
通常はチェリー(皮付き:赤又は黄色*品種によって皮の色は異なります)の状態で取引されます...
伝統?風習なのでしょう〜多分気候の影響も大きいのかもしれませんが、インドネシアのスマトラ島では昔からチェリーの状態ではなく、皮を剥いて洗い

発酵槽を経て水分値30~45%まで一時乾燥させたまだ濡れた状態の殻/パルプ付きのコーヒー豆の状態(GABAHガバ)で取引され、

買い取ったGABAHの殻付き豆を水分値30%まで乾燥させ(LABUラブ)、その後脱穀し、生豆の状態(ASLAアスラ)で最終水分値11%程度になるまで乾燥させて仕上げます。
特徴としては通常のウォッシュドやパルプド・ナチュラル(ハニー)で仕上げた生豆より黒緑色で少しよじれているシェイプの生豆となります。

*レッドハニー

*スマトラ式
インドネシアのスマトラ島では中米や南米、アフリカの主要産地と異なり亜熱帯性の熱帯雨林気候なので乾季でも雨はよく降りますし、なかなか乾燥状況には恵まれていない地域性がこのスマトラ式の偶然いや必然の精製となり、その『スパイシーな味わい』に魅了された中米の生産者達があえて同じ様なGABAH→LABU→ASLAの工程を踏んでスマトラ式に取り組んでいるなんて話を聞くと本当に生産者さん達の『努力』や『探究心』には脱帽です。
日本では『マンデリン』と呼ばれるコーヒーはスマトラ式で仕上げたコーヒーで通常は深煎り/スパイシーで華やかな香りが特徴です。