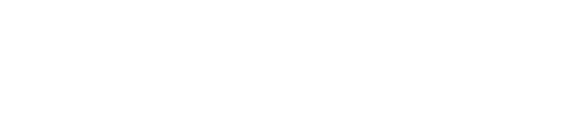コーヒーの精製について〜自称Mr.ファーメンテーション(発酵)のオタクな世界観Part.1
どうしてもコーヒー業界の人は、当たり前の様に『業界用語』で解説してしまいがちです...
身近な嗜好品ではワイン、日本酒...僕はお酒が飲めないのでコーヒーにハマった経緯は今まで店頭や雑誌のインタビューなどで語ってきた既成事実なので、僕が以下の様にお酒の事を語っても説得力はないとは思いますが...
是非コーヒーに興味を持ってもらいたいので少し語ってみます。
先ずはワイン
白と赤の大きな違いは
『白』ブドウの果汁だけで作られる
『赤』葡萄の果汁、果皮、種子を使って作られる
*赤ワインは発酵後に圧搾しますが、白ワインは圧搾前に発酵される...発酵が伴います。
日本酒
色々な醸造方法*お米、米麹、水を発酵させて作る
純米、純米吟醸、純米大吟醸、特別純米大吟醸、吟醸、大吟醸、本醸造、特別本醸造...
その中でも分類として、
『純米』米・米麹/精米比率の規定はない/米だけで作っている
『吟醸』米・米麹・醸造アルコール/精米比率は60%以下
『大吟醸』米・米麹・醸造アルコール/精米比率は50%以下
『本醸造』米・米麹・醸造アルコール/精米比率は70%以下
ビール/発泡酒
成分は麦芽(発芽させた大麦・モルト)、ホップ(ハーブの一種)、酵母、水
ビールの発酵は麦汁中の糖分が酵母によってアルコールと二酸化炭素に分解される生化学反応で、ビールの味わいは酵母の種類によって決まり、発酵方法には『上面発酵』と『下面発酵』の2種類がある...
『上面発酵』エールビール*ペイエール、スタウト、アルト、ヴァイツェンetc
『下面発酵』ラガービール*ピルスナー、ミュンヘナーetc
お酒が飲める方はこの様な沢山の味わいを楽しめる!僕にとっては羨ましく感じます。
いよいよ本題です。
コーヒー好きの人でもあまり実感されている方は少ないのですよね?
コーヒー豆=発酵食品
我々コーヒー屋が多用する業界用語の際たる呼び名が精製...
発酵のさせ方による仕上げ方に起因しています。
フラホワでも普通に
①Washed(フーリー)ウォッシュド/水洗式
②Natural ナチュラル/非水洗式
③Honey ハニー/パルプド・ナチュラル/セミウォッシュド
④Sumateraスマトラ式 セミウォッシュド
⑤Anaerobicアナエロビック 嫌気性発酵
⑥過去にはワイニー、ファンキーナチュラル、ペルラネグラ、
スウィートシャワー、 ダブルファーメンテーション etc
数え上げたらキリがありませんが、全て生産者達の努力の結晶=『美味いコーヒーを作り出す努力』だと理解して欲しいです。
古来コーヒー産地では水源の確保が困難...今でもその環境ははあまり変わっていない地域が多いです。そもそも自生していたエチオピア(コーヒー発祥の国)や15世紀頃にイエメンで始まった商業的コーヒー栽培では収穫したチェリーをそのまま天日干しで仕上げる方法(②ナチュラル)、ナチュラルこそが伝統的な精製方法でした。
『生産国』に行けばそのインフラ環境に驚かされます...今でも電気や水道の確保が困難な産地は沢山存在していますし、我々『消費国』の感覚は通じません。

ナチュラルでのコーヒー生産はウォッシュドの3倍(乾燥工程/時間&製造量の不確定化*ロス(不良豆の把握)確認遅延)手間が掛かります。コーヒー業界の産業革命*大量消費時代の到来により、現在では一般的なコーヒー精製では①ウォッシュドが主流となっています。

*今でも東ティモールなど多くの産地ではこの様に手動でウォッシュドを仕上げている国も多く、ウォッシュドの原点です
これから精製を語る上で、先ずはコーヒー豆の構造について復習です。
コーヒーノキ(学術名)アカネ科のコーヒーノキ属に属する植物の総称。
日本語でコーヒーの木と偶然一緒ですので是非カタカナで覚えて欲しい(笑)
アラビカ/ロブスタ/リベリカ3大品種からなり、エチオピアアのコーヒーこそがルーツ(原種/Herloom)なのです。
精製を語る上で一度コーヒー豆の構造を簡単に解説しておきます。


コーヒー豆は図や写真の様に外皮に包まれた実であり、この外皮を水洗で剥がす(パルピング)プロセスが①ウォッシュドであり、外皮とパーチメント(殻)の間にパルプ(僅かの果肉)とミューシレージ(粘質物)が付いています。
19世紀に中南米(パナマ説があります)で始まったウォッシュド精製...
その精製方法は効率化かつロスを未然に把握し生産量を伸ばせる意味でコーヒー業界の第一次産業革命だったと思います。
パルパー(皮剥き機)の登場により、一気にコーヒー豆産業は飛躍して行きました!



伝統的な②ナチュラルでの精製ですと、乾燥過程でカビや虫食い、突然の雨による被害(再乾燥の繰り返し/洗濯物の様なイメージです)を受け易く生産量の確保はおろかクウォリティの確保が困難でありました。
そこで①ウォッシュドの精製は、パルパーによる水で洗い流しながら皮を剥き、チェリーの中身から豆を取り出し、その後水にさらされた豆は表面に付着しているミューシュレージ(粘液質)の分解を行いながら発酵過程に...

産地に行って『チェリーが甘い!』『シロップみたいに甘め〜!』...こんなコメントを聞くかも知れませんが、このミューシュレージを舐めて『甘さ』を感じているのです。
完熟したコーヒーチェリーは本当にサトウキビの様に甘く、淡い酸(桃や洋梨の様な)を堪能出来ます...残念ながら産地に行かないと味わえません。味わう為にはコーヒーノキ自体を育てて3年以上経って白くジャスミンの様な香りの花が咲き、その後緑色の豆が出て赤く完熟したところで摘み、パク付く!
『甘さ』を知るにはそれしかないのです...
実際に生豆(チェリーを剥いて出てくる正にコーヒー豆)は硬くて噛める様なモノではなく、消化出来ずに糞として排出されたジャコウネコのコピ・ルワック(高級豆)はジャコウネコの体内で消化出来ずに発酵されたコーヒー豆として『希少価値』の極めです...
発酵の話に戻りますが、通常は皮を剥かれたコーヒー豆は表面にミューシュレージがまだ付いていて発酵槽(皮剥き後に落ちてくる場所=槽)で一晩寝かされます。その際、水を少し張る事で微生物が豆の表面のミューシュレージを分解しながら穏やかな発酵処理がなされます。
翌日、発酵槽から繋がる水路を経てその水路を流しながら再度ゴシゴシと丹念にミューシュレージを洗い流す仕上げのウォッシュ作業を行います。
その際に『浮いてくる豆』を未熟豆と判断し、沈んでいる完熟豆との仕分けを水洗作業と同時に行い、分解されたミューシュレージを落とした生豆を乾燥棚で干す。

この様にして精製されるのが①ウォッシュドで、②ナチュラルより大幅に乾燥時間が短縮され1週間位で一定の水分量(通常11〜12%)まで乾燥され仕上がります。
乾燥が早い為、カビの被害も少なく、虫食いなども発見し易い、不良豆の摘出が乾燥させながら同時進行で進める事が可能です。
以上2種類がメジャーな精製方法と言われております。